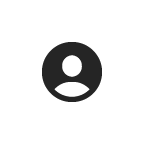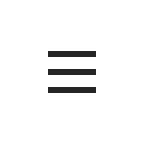国債の世界に「タダ飯」なし
「自国通貨建てならば国債はいくらでも発行することができる。日本銀行が円を発行しながら国債を購入すればよいからだ。それを続ければデフォルト(債務超過)は起きないので、財源がなくても財政支出はいくらでも拡大できる」という声が日本のSNS上ではなぜか非常に多い。
筆者は仕事柄、機関投資家や銀行、証券会社で国債を実際に売買しているプロたちと日常議論しているのだが、そういった現象に強い危機感を表す人が最近増加している。根本的に間違っているからである。
この原稿は出張先のニューヨークで書いている。当地の金融市場参加者に冒頭の話をすると、「いや、それはあり得ないでしょ」といった反応が返ってくる。一言でいえば、「フリーランチ(タダ飯)は存在しない」ということになる。
自国の債務に悲鳴を上げた英国人女性
2010年~11年にかけて筆者がロンドンに滞在していたとき、財政に対するイギリス人と日本人の感覚の大きな差を感じる出来事があった。ホームステイ先の大家のご婦人(60代後半)とダイニング・ルームで夕食をとっていたときのことである。
BBCのテレビ・ニュースが、英政府の債務膨張を報じていた。2008年にグローバル金融危機が勃発。混乱に対処するため当時のブラウン労働党政権は政府支出を大幅拡大させた。2010年に政権を奪取した保守党のキャメロン政権は、増税と大胆な補助金カットによる過激な財政健全化策に着手しようとしていた。しかし前政権の政策の余波で2010年の政府債務残高のGDP比(経済規模比)は100%を超える見通しだとBBCは解説していた。
この100%超という数字を聞くや否や、大家のご婦人は世も末だという感じで、悲鳴を上げ、首を振りながら深い嘆きを表した。彼女は零細企業を経営していたが、特に経済学に詳しいわけではなく、財政の知識に関しては平均的なイギリス人女性だったと思われる。それなのに100%越えの政府債務の状況をとても心配していた。
日本ではそういう反応はあまり見られそうにないだけに、非常に不思議に感じられた。話しているうちに、過去に英政府の財政が悪化したときに、ポンド安や金利上昇が起きて、家計や会社経営が苦しくなった実体験を持っていたことが分かってきた。
彼女に「あなたはエコノミストだと聞いたけど、日本政府の債務はどうなの?」と聞かれた。ちょうどその日使った金融機関向けのプレゼン資料があったので示しながら、「200%を超えてます」と説明した。すると彼女は驚愕のあまり目が点になった。
「じゃあ、金利は高いんでしょう? 預金金利はいくら?」
「ほとんどゼロ%です」
「え、じゃあVAT(付加価値税、日本の消費税に相当)は?」
「5%です」
「そんな低い国があるの? 信じられない」
そう言って婦人は大笑いを始めた(当時のイギリスのVATは17.5%で、翌2011年初に20%へ引き上げられることが予定されていた)。
彼女にとって筆者は「不思議の国のアリス」の世界から来た人間に見えたようだ。しかし、そんな経済がいつまでも続くことが感覚的に怪しく感じられたらしく、「この人は家賃をちゃんと納め続けられるだろうか」といった疑念のまなざしがちらりと筆者に発せられた。
日本の場合、これまでは政府債務がいくら増えても幸いなことに国民は大きな痛みを感じずに済んできた。災害と同じで、例えば津波が長く来ないと人々のそれへの警戒心は薄らいでしまう面がある。
低金利の「ぬるま湯」時代が終わる
下図の水色の縦棒は国債発行残高であり、赤い線は国債に政府が支払う金利=利払い費である。利払い費が過去最大だったのは1991年の11兆円だった。
その年の国債発行残高は172兆円だ。2024年のそれは1,104兆円であり、なんと6.4倍に増えた。ところが同年の利払い費は8.2兆円しかなく、91年よりも少ない。なぜなら、この間、国債の発行金利(黄色い線)が大きく低下してきたからである。
このため「国債はいくらでも発行できる」という誤解が国民や政治家の間で広まってしまったのだと思われる。
とはいえ、これまで金利が低下してきた原因は、インフレ率が低かったことと、インフレを押し上げるために日銀が超低金利策や国債大規模購入策を実施してきたことにある。しかし今や先進国でインフレ率が最も高い国は日本になってしまった。それなのに日銀は政策金利を不自然に低く抑えている(下図)。インフレを定着させたいことに加え、国債の金利が跳ね上がったら大変だと日銀は強く恐れているからである。
その結果、政策金利からインフレ率を差し引いた実質政策金利は海外と比べ、圧倒的に低い状態にある。これが行き過ぎた円安の修正を阻む大きな要因といえる。銀行へのわれわれの預金の利子はインフレに負けて元本が目減りしており、資金が海外に流れやすくなっている。円安は食品やガソリンなど生活必需品の価格を高騰させている。つまり、国債大規模発行のツケはすでに円安と物価高騰という形で国民を苦しめ始めているのだ。
今後の国債発行金利は、中長期的にはインフレにある程度合わせて上昇せざるを得ないだろう。そうなると、国債の利払い費が増大して、財政を圧迫していく。国債をいくらでも増発できるという時代は明らかに終わってしまっている。
為替レートの下落と物価高
「自国通貨建てなら国債をどんどん発行できる」という考え方の大きな過ちのひとつは、為替レートへの影響を忘れている点にあるといえるだろう。
中央銀行が国債を購入しながら(あるいはシンプルに中銀が政府に資金を貸し付けながら)政府が減税や補助金給付などの支出拡大を続けた場合、最終的には物価上昇と為替レート下落が相互に影響し合いながら、そのスパイラルが深刻に進んで行くことになる。
現実にそうなった事例は、古今東西枚挙にいとまながない。1990年以降だけでざっと数えても、それによって年間のインフレ率が100%を超えた国は43カ国、1000%を超えた国は18カ国、1万%を超えた国は3カ国ある。しかも超インフレに一度陥ると、1年では収まらず、数年続いてしまうケースがたびたび見られる。
そういった状況下でも政府が発行する国債を中央銀行が買い続ければ形式上はデフォルトにならない。しかしながら高インフレになる前に発行された国債を持っている人は、その実質価値がほとんどなくなっていることに気づかされるだろう。
財政を研究している著名な経済学者らは、そういう事例も事実上の国債のデフォルトと見なしている。「形式的にはデフォルトではない」と主張したところで無意味といえる。やはり「フリーランチ」は存在しないのである。
バナー写真:報道陣に公開された新紙幣の表刷印刷工程=2024年6月、東京都北区(時事)
Latest Nippon News (jp)
- 水産白書:2023年の水産物生産額は1兆6853億円 イワシ類の価格上昇で増加海面漁業の生産額は9534億円で、同4%増。海面養殖業はノリの価格上昇で同10%増の5956億円だった。内水面漁業・養殖業は1363億円で3%減だった。生産量は前年比2%減の383万トン。この量は、生産量ピーク時の1984年(1282万トン)の約3割に当たる。養殖業による水産物生産量は全体の23%にあたる約88万トン。しかし、生産額は43%を占める7169億円となっている。23年度の食用魚介類の自...
- 相撲部屋の動画発信は角界の未来を救うのか:伝統堅持へルール強化も力士が一斉に「ごっちゃんです」特濃つけ麺がテーブルに運ばれると、力士たちは手を合わせて「ごっちゃんです」。一斉にスープにつけた麺をすすり、お代わりをする。力士たちは「魚介の味がめっちゃ濃厚です」「最高です」と食レポ。サイドメニューのから揚げも次々に口へ運ぶ。二子山部屋のYouTube動画「【三田製麺をすする力士】全部のせ特濃つけ麺・たまごかけ麺・唐揚げ・鯛だし塩つけ麺」は、親方と力士たちが店舗の2...
- 今日は何の日:7月1日安倍政権が集団的自衛権容認2014(平成26)年 安倍晋三内閣が集団的自衛権の行使を限定容認することを閣議決定。従来、内閣法制局の解釈では集団的自衛権の行使は全面禁止とされていたが、新たな憲法解釈により可能にした。安全保障環境の激変などを踏まえたもの。関連記事激動する国際情勢下の日米韓関係:キャンプデービッド精神にのっとった日韓協力強化を日本と欧州、NATOで抑止を強化する日米韓の安保協力強化:現...
- 〈1970年の今日〉6月30日 : 初代「トミカ」6車種発表憧れのスポーツカーが手のひらに1970(昭和45)年 玩具メーカーのトミー(現タカラトミー)が、8月に発売するミニカー6車種を発表。「ブルーバードSSSクーペ」「コロナ マークⅡハードトップ」「クラウン スーパーデラックス」「クラウン パトロールカー」「トヨタ2000GT」「フェアレディZ432」の6車種。発売当初の価格は180円。輸入物の高価なミニカーしかなかった時代、身近な国産車をモデルにした...
- ユーラシアの戦争を横目に見ながら進む中国の首脳外交:その地域戦略を探るユーラシアの戦争と合従連衡目下、アメリカのトランプ政権が示す「新時代」のアメリカの姿は、従来のアメリカとは大きく異なり、また予測可能性が低いこともあって世界にはさまざまな動揺が広がっている。また、世界全体は多極化に向かっているとされるが、多数の極と極との関係性もまた不分明だ。そして、ユーラシアではウクライナと中東で戦争が生じており、そこにインドとパキスタンの紛争も加わっている。そして、それぞれの戦...
- 【2024年度出国税】5年ぶりに最高収入を記録 円安追い風、インバウンド増加で1人当たり1000円財務省が発表した24年度の国際観光旅客税の収入は481億円で、これまでで最高だった19年度の443億円を上回った。一般会計の年度は4月から翌年3月末までだが、同税の集計は5月末までに納付された分は前年度収入としてカウントする。発表された24年度の税収額は4月末までの集計であり、最終的な数字はさらに拡大する。税収増の大きな要因は、円安と訪日客(インバウンド)の増加だ。日本政府観光...