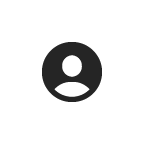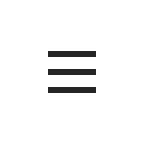鎌倉・建長寺発祥の禅文化:坐禅や精進料理で古来の教えを感じる
Guideto Japan
800年以上の歴史ある古都・鎌倉(神奈川県)は、武士が崇敬した禅宗の聖地。禅宗寺院の中で最も格式高い建長寺を訪ね、境内の風景や修行の中に「禅の心」を感じたい。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
宗教都市の中核を成す鎌倉五山筆頭
相模湾に面し、三方を山に囲まれた鎌倉は、狭いエリアに123もの寺院が肩を寄せ合う。中でも鎌倉幕府が庇護(ひご)した臨済宗は42寺と3分の1を占める。

建長寺の三門(山門)。後ろに並ぶ仏殿、法堂(はっとう)、唐門と共に国の重要文化財に指定される 写真=原田寛
臨済宗は、後の時代に開宗した曹洞(そうとう)宗、黄檗(おうばく)宗と共に、坐禅(座禅)修行によって悟りを目指すことから「禅宗」と呼ばれる。鎌倉幕府が禅宗寺院を格付けした「五山制度」では、第1位の建長寺から順に円覚寺(えんがくじ)、寿福寺、浄智寺(じょうちじ)、浄妙寺の5寺が選ばれた。
鎌倉五山はいずれも存続しているが、中でも建長寺は筆頭にふさわしい風格を保つ。日本初の禅の専門道場として、1253(建長5)年に創建された当時の文化も色濃く残っている。

境内最奥の高台から一直線に並ぶ伽藍(がらん)を望む 写真=原田寛
実際に訪れると、あちらこちらに禅宗寺院の代表的な要素が感じられる。その一つが伽藍の配置。総門、三門、仏殿、法堂、方丈などの主要な建物が一直線に並んでおり、典型的な中国禅宗様式をとどめている。
三門から仏殿へと続く参道の両脇には、寒さに強いヒノキ科の常緑樹・柏槙(ビャクシン)の木が整然と並ぶ。その生命力を貴ぶ中国禅宗にならい、開山の蘭渓道隆(らんけい・どうりゅう)が宋(当時の中国)から携えてきた苗木を植えたと伝わる。樹齢は760年を超え、幹回りは7メートルにも及ぶ堂々たる姿は、貴重な創建当時の記念碑ともいえる。
参道右手の鐘楼にある梵鐘(ぼんしょう)は、1255(建長7)年の鋳造で国宝の指定を受ける。古調の優美な形が特長で、同じく国宝の円覚寺の鐘、市内最古の常楽寺の鐘と共に「鎌倉三名鐘」と呼ばれている。
仏殿に安置する本尊は、死後の世界で亡者を救うと信じられている地蔵菩薩(じぞうぼさつ)。禅宗寺院の本尊は釈迦如来(しゃかにょらい)が一般的なので非常に珍しい。

台座を含めて約5メートルの本尊・地蔵菩薩(仏殿は2027年7月までの予定で補修工事中) 写真=原田寛
境内を奥へと進むと、かつては住職の居室だった方丈があり、裏手の庭園では芝生が池を囲んでいる。日本庭園といえば苔(こけ)むしたイメージがあるが、それは近世以降に広まった様式。芝を敷いていたとする専門家の意見を参考に、古い時代の庭園様式を復興したという。

池を中心にした建長寺庭園は国指定史跡・名勝。現在、橋は架かっていない 写真=原田寛
坐禅のみならず日々の食事も修行
境内東の丘の上にある道場では、今も僧侶たちが日々、坐禅を中心にした厳しい修行に励んでいる。日常の食事は一汁一菜と簡素で、肉や魚など動物性の食材は一切口にしない。調味料もすべて植物由来のものを使う徹底ぶりだ。
汁物はシイタケや昆布でだしを取り野菜や豆腐などを入れた「けんちん汁」で、栄養も食べ応えも十分。今や全国的に家庭の味として定着しているけんちん汁だが、「けんちょう汁」が語源とされ、建長寺発祥の鎌倉名物である。
また、食事には必ず大根の漬物「たくあん」が添えられる。注ぎ入れた湯とたくあんで器の中を掃除してから、最後に湯ごと飲み干し、米一粒たりとも残さないのが決まり。修行僧たちは生き物の命を大切にする、無駄をなくすという、古来の禅の精神から生まれた習慣を厳しく守っている。

毎年1月には三浦半島の大根農家を回って托鉢(たくはつ)し、たくあんを作る 写真=原田寛
修行の邪魔になるため、僧堂に続く参道は立ち入り禁止。ただし、境内のボタンが満開になる晩春だけは特別に参拝者が散策できる。

参道のボタン。見ごろの時期は神聖な修行場に足を踏み入れるまたとない機会 写真=原田寛
境内にはさまざまな禅の文化が凝縮しているが、やはり最も重要なのは基本修行の坐禅である。背筋を伸ばして姿勢を正し、呼吸を整えるに従って、自然と邪念が払われて心が落ち着く。建長寺では毎週金曜と土曜に、初心者でも参加できる坐禅会を開催している。日本最古の修練の場で静かに坐せば、日常を忘れて己と向き合う新鮮な体験が得られるだろう。

坐禅体験は金曜・土曜の午後3時30分から1時間(開始15分前に集合)。予約不要、拝観料のみで参加できる。事前に申し入れすれば椅子を用意してくれるので、畳に坐れなくても安心 写真=原田寛
写真・文=原田寛
バナー写真:境内正面からの伽藍展望 写真=原田寛
Latest Nippon News (jp)
- 今日は何の日:5月14日昭和の大横綱大鵬が引退表明1971(昭和46)年 第48代横綱大鵬が引退会見。前日、大相撲夏場所で、小結貴ノ花(当時)に敗れたのが現役最後の一番となった。1960年代に活躍し、ライバル柏戸とともに「柏鵬 (はくほう) 時代」を築いた。優勝32回、6連覇2回、45連勝などを記録し、昭和の大横綱と称された。69年、優勝30回を記念して日本相撲協会から一代年寄「大鵬」の名跡を贈られた。→ こち...
- 2025年のプロ野球選手平均年俸は4905万円:前年比4.1%増―選手会調査平均年俸は前年に比べ192万円(4.1%)の増加。総額は355億5888万円で、総額としては過去最高を更新した。リーグ別ではセントラル・リーグが4.2%増の5128万円(359人) 、パシフィック・リーグが4.2%増の4685万円(366人)で、3年連続でセが上回った。年俸の中央値(725人中で真ん中の順位にいる選手の年俸)は1900万円で、前年より100万円増加した。平均年俸は、1986年に10...
- 「もろ刃の剣」SNSが日本人の政治意識・投票行動に与える影響インターネットは政治参加を活性化させる?民主政の「主人公」は私たち有権者であるが、政治闘争や政策形成の現場を直接見聞きする機会は限られるため、それらに関する情報の入手は各種メディアに頼らざるを得ない。日本の国政選挙時に「明るい選挙推進協会(明推協)」が行っている全国調査((明るい選挙推進協会(2025)『第50回衆議院議員総選挙全国意識調査―調査結果の概要―』。))によれば、有権者が政治や選挙に関...
- 『トワイライト・ウォリアーズ』のヒットに見る香港映画とアイデンティティーの現在『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』はなぜ日本でヒットした?香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』が、1月17日の劇場公開後、3カ月で興行収入4億円を突破した。当初は中規模の上映だったが、熱狂的な口コミやリピーター効果を受けて上映館を拡大し、4月には日本語吹き替え版の上映も始まっている。香港映画が日本でこれほどの話題を呼んだのは約20年ぶり。もともと香港では興行収入1億1...
- 日産、過去最大に迫る6708億円赤字に転落―25年3月期 : 国内含む7工場、2万人を削減へ日産自動車が5月13日発表した2025年3月期決算(連結)は、売上高が前期比横ばいの12兆6332億円で、純損益は6708億円の赤字(前期は4266億円の黒字)に転落した。赤字幅は過去最大だった2000年3月期の6843億円に迫る。新モデルの投入が遅れ、中国や米国などで販売が落ち込んだほか、国内外の工場などの資産価値を見直し5000億円を超える減損処理をした。業績の悪化を受けて、日産ではリストラを...
- 経常黒字、過去最大30兆円―国際収支速報 : 円安で配当金など増加、貿易は4年連続赤字財務省が5月12日発表した2024年度の国際収支統計(速報)によると、海外とのモノやサービスの取引、投資収益の状況を示す経常収支は30兆3771億円の黒字で、黒字幅は比較可能な1985年度以降で過去最大だった。輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は4兆480億円の赤字。輸出は半導体製造装置や自動車が伸びたものの、輸入はパソコンやスマートフォンなどが増加した。貿易赤字は4年連続。一方、海外からの利子...