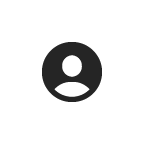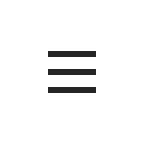無料で絶景を楽しむ! 訪日客が続々…自治体が庁舎展望室をつくるワケは?
国内の自治体庁舎は高層化が進み、多くが入場無料の展望室を備えている。その代表格である東京都庁には、都内の街並みだけでなく富士山などの絶景が気軽に楽しめるとあって訪日外国人が詰めかけている。都内の自治体庁舎の展望室を巡りながら、その設置意義を考えてみた。
累計利用者は5500万人
東京・西新宿にそびえる東京都庁舎は1990年に竣工した。第1本庁舎の高さは243メートルで、竣工当時は国内で最も高い建築物だった。2本の塔がそびえ、それぞれ高さ202メートルの45階には、一般来庁者が無料で利用できる展望室がある。庁舎はオープンから35年がたって東京のランドマークとしてすっかり定着し、展望室の利用者は累計で約5500万人に上る。コロナ禍の影響で年間利用者数は2020年が15万人、21年は7万人と一時落ち込んだが、24年は160万人と大きく回復した。

東京都庁の展望室からは東京スカイツリーなど都内の風景が楽しめる(東京都提供)
北塔の展望室には、眺望とともに軽飲食が楽しめるスペースが設けられ、夜間は貸し切りイベントやパーティーを開催できる場所としても提供されている。南塔の展望室には、芸術家の草間彌生氏がデザインを監修した「都庁おもいでピアノ」が置かれ、誰でも自由に演奏できる。

芸術家の草間彌生氏がデザインを監修したピアノ。誰でも自由に演奏を楽しめる(筆者撮影)
利用者の大半は都外からの観光客で、昨今は日本人よりも訪日外国人が圧倒的に多い。00年代に中国、韓国などアジアからの訪日客が目立つようになり、最近はヨーロッパや中南米などさまざまな国から人々が集まるようになっている。

東京のランドマークとして定着した東京都庁第1庁舎。2つに分かれた塔が特徴だ(筆者撮影)
外国人観光客が長蛇の列
取材で4月に都庁展望室を訪れると、入場の受付をする庁舎1階には長蛇の列ができており、「45分待ち」の札が示されていた。かつては入場待ちなどなく展望室へ向かうことができたが、昨今の人気ぶりはすさまじい。

東京都庁の展望室への入場待ち時間を知らせるサイン(筆者撮影)
展望室には2011年度から英語、中国語、韓国語で案内する通訳ボランティアが常駐している。ボランティアスタッフの女性は、「最近はヨーロッパからの観光客が増えているようです」と話し、外国人観光客の対応に追われていた。
フランスから訪れていたウーヤンビさんは、日本人の妻と帰省がてら訪日することが多く、すでに7~8回は都庁展望室に来ているというリピーターだ。日本通のウーヤンビさんは、「横浜のランドマークタワーや東京スカイツリーと比べても、都庁展望室からの景色は素晴らしい」と絶賛する。
イタリア人のシロ・ピッシさんは2回目の日本旅行。「ここは動画サイトで知り、楽しみにして来た」と話し、携帯で盛んに記念の写真を撮っていた。外国人観光客にとって、無料で立ち寄れる展望室は魅力的なスポットであり、取材した多くの人が「これだけの絶景を無料で楽しめることが信じられない」と口を揃えた。
「行政への理解」のため
都庁舎は東京都という巨大行政機関のオフィスであり、本来ならば無料の展望室は必要ない。ではなぜ、業務に不必要なスペースを設けるのだろうか?
「都庁舎を訪れる人が眺望を楽しみながら東京に親しみを感じてもらい、東京のことや都政を理解する一助ともなるようにと設置した」。こう説明するのは、東京都庁舎管理課の平塚健次課長だ。
日本の各自治体は、住民が行政に親しみを持ちやすいようにと広く庁舎を開放し、誰もが比較的自由に出入りできるようにしてきた。それを当たり前のように受け止めてきた日本人の意識が、自治体による展望室の設置、無料開放の根底にあるようだ。
日本の建築史や都市史が専門で、都道府県庁舎に関する著書がある武庫川女子大学の石田潤一郎教授は、「丸の内にあった旧都庁舎には、都民が集まれる広場が設けられていた。こうしたオープンスペースがつくられる背景には、庁舎が税金によって建設された公共施設であり、多くの住民が使える空間にするという行政の意識が働いているためと考えられる」と話し、「自治体の庁舎が高層化するのに伴い、展望室がそうしたオープンススペースの役割を担うようになっている」と解説する。
高層化の背景
石田教授によると、法律的な面から庁舎の高層化を後押ししたのは1963年の建築基準法改正だった。改正前まで建物の高さは約31メートルに制限されていた。この数字は戦前使われていた尺貫法が基になっている。約31メートルは100尺に相当することから、同制限は100尺規制と呼ばれた。
法改正で100尺規制は撤廃され、高度成長期における地価上昇、土地の高度利用の需要に応じるビル高層化に道が開けた。68年には、高さ約147メートルの霞が関ビルディングが誕生して世間の耳目を集めた。
自治体庁舎の高層化は65年竣工の岩手県庁舎が先駆けだが、100尺規制の撤廃によって全国の自治体がすぐに高層化を進めたわけではない。57年竣工の旧都庁舎がそうであるように、多くの自治体は戦災で庁舎を喪失し、戦後の復興期に再建した。そのため法改正時はまだ新庁舎の供用から日がたっておらず、新たな建て替えのタイミングは80年代後半から90年代に集中することになる。
時代が進むにつれて行政の管轄は増え、保管しなければならない行政文書、資料は膨れ上がってきた。特に人口が集中する大都市では、地価上昇により新たな庁舎拡張用地の確保が困難になってくる。庁舎の水平拡大ではなく、高層化が大都市で志向される背景には、そうした事情があった。
必須アイテム化?
東京23区内では、1990年代に区庁舎の建て替えや移転の計画が始まり、今も続いている。練馬区は96年に高さ約93.8メートル、地上21階建て、文京区は99年に高さ約142メートル、地上28階建ての区庁舎をそれぞれ新たに建設した。文京区庁舎は23区内では最も高く、練馬区庁舎は2番目だ。文京区庁舎は2026年12月まで改修工事のため閉鎖しているが、両区庁舎とも無料開放の展望室を備えている。練馬区総務課の梶山奈緒さんは、多くの人に足を運んでもらえるように「(展望室から)富士山や東京スカイツリーが見える眺望を目指した」と説明する。

住宅街の中に立つ練馬区庁舎。展望階にはレストランが営業している(筆者撮影)
世田谷区は24年5月、10階に展望ロビーを備えた新庁舎東棟の供用を始めた。「高層」の庁舎ではないが、「周りに高い建物がなく、世田谷の街並みを一望できる」(同区庁舎管理担当課の山地弘係長)。オープン時には、児童文学者で名誉区民だった故中川李枝子さんの絵本作品『ぐりとぐら』のパネル展示をロビーで開催し、大勢の来場者でにぎわった。

世田谷区庁舎。周辺に高層建築がないため、展望ロビーからは富士山などを遠望できる(筆者撮影)
一般来庁者にとって魅力的な設備を庁舎に付加することで、行政側は住民との距離を縮められると安易に考えるが、それほど単純な話ではない。住民向けのイベントスペースとして活用される例はそれほど多くはなく、実際には「観光設備」の色合いが濃いうえ、肝心の観光客を呼び込めていないケースも散見される。にもかかわらず、行政の常である「横並び意識」が働くのだろうか、自治体が庁舎を一新するたびに展望室を必須アイテムのように備える傾向は、全国的に強まっている。
石田教授は「庁舎は頻繁に建て替えるものではない。他の自治体がやっているからといって模倣するのではなく、庁舎には何が必要なのか? 本当に展望室は必要なのか?―といったことを長期的な視点で考えるべきだ。まずは住民や議会の理解を得ることが重要だ」と指摘する。
展望室を備える自治体庁舎が全国で増え続けているものの、都庁のように利用者があふれ、自治体のPRや住民サービスに大きく貢献している庁舎展望室は限られている。各自治体は、それぞれが持つ展望室をどのように活用するのかをしっかり検討するべきだろう。さもなければ「宝の持ち腐れ」になる。
バナー写真:東京都庁の展望室から眺めた東京の夜景(東京都提供)
Latest Nippon News (jp)
- 今日は何の日:5月15日沖縄が本土復帰1972(昭和47)年 敗戦後米国の施政権の下にあった沖縄が、71年の佐藤栄作首相、リチャード・ニクソン米大統領による沖縄返還協定調印に基づき、日本に返還された。通貨は米ドルから円に替わり、本土との往来にパスポートは不要になった。これまでさまざまな振興策が実施されてきたが、返還50年以上を経てもなお、「基地の島」の現実からは逃れることができない。関連記事沖縄基地のもう一つの現実 : ...
- 今日は何の日:5月14日昭和の大横綱大鵬が引退表明1971(昭和46)年 第48代横綱大鵬が引退会見。前日、大相撲夏場所で、小結貴ノ花(当時)に敗れたのが現役最後の一番となった。1960年代に活躍し、ライバル柏戸とともに「柏鵬 (はくほう) 時代」を築いた。優勝32回、6連覇2回、45連勝などを記録し、昭和の大横綱と称された。69年、優勝30回を記念して日本相撲協会から一代年寄「大鵬」の名跡を贈られた。→ こち...
- 2025年のプロ野球選手平均年俸は4905万円:前年比4.1%増―選手会調査平均年俸は前年に比べ192万円(4.1%)の増加。総額は355億5888万円で、総額としては過去最高を更新した。リーグ別ではセントラル・リーグが4.2%増の5128万円(359人) 、パシフィック・リーグが4.2%増の4685万円(366人)で、3年連続でセが上回った。年俸の中央値(725人中で真ん中の順位にいる選手の年俸)は1900万円で、前年より100万円増加した。平均年俸は、1986年に10...
- 「もろ刃の剣」SNSが日本人の政治意識・投票行動に与える影響インターネットは政治参加を活性化させる?民主政の「主人公」は私たち有権者であるが、政治闘争や政策形成の現場を直接見聞きする機会は限られるため、それらに関する情報の入手は各種メディアに頼らざるを得ない。日本の国政選挙時に「明るい選挙推進協会(明推協)」が行っている全国調査((明るい選挙推進協会(2025)『第50回衆議院議員総選挙全国意識調査―調査結果の概要―』。))によれば、有権者が政治や選挙に関...
- 『トワイライト・ウォリアーズ』のヒットに見る香港映画とアイデンティティーの現在『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』はなぜ日本でヒットした?香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』が、1月17日の劇場公開後、3カ月で興行収入4億円を突破した。当初は中規模の上映だったが、熱狂的な口コミやリピーター効果を受けて上映館を拡大し、4月には日本語吹き替え版の上映も始まっている。香港映画が日本でこれほどの話題を呼んだのは約20年ぶり。もともと香港では興行収入1億1...
- 日産、過去最大に迫る6708億円赤字に転落―25年3月期 : 国内含む7工場、2万人を削減へ日産自動車が5月13日発表した2025年3月期決算(連結)は、売上高が前期比横ばいの12兆6332億円で、純損益は6708億円の赤字(前期は4266億円の黒字)に転落した。赤字幅は過去最大だった2000年3月期の6843億円に迫る。新モデルの投入が遅れ、中国や米国などで販売が落ち込んだほか、国内外の工場などの資産価値を見直し5000億円を超える減損処理をした。業績の悪化を受けて、日産ではリストラを...